
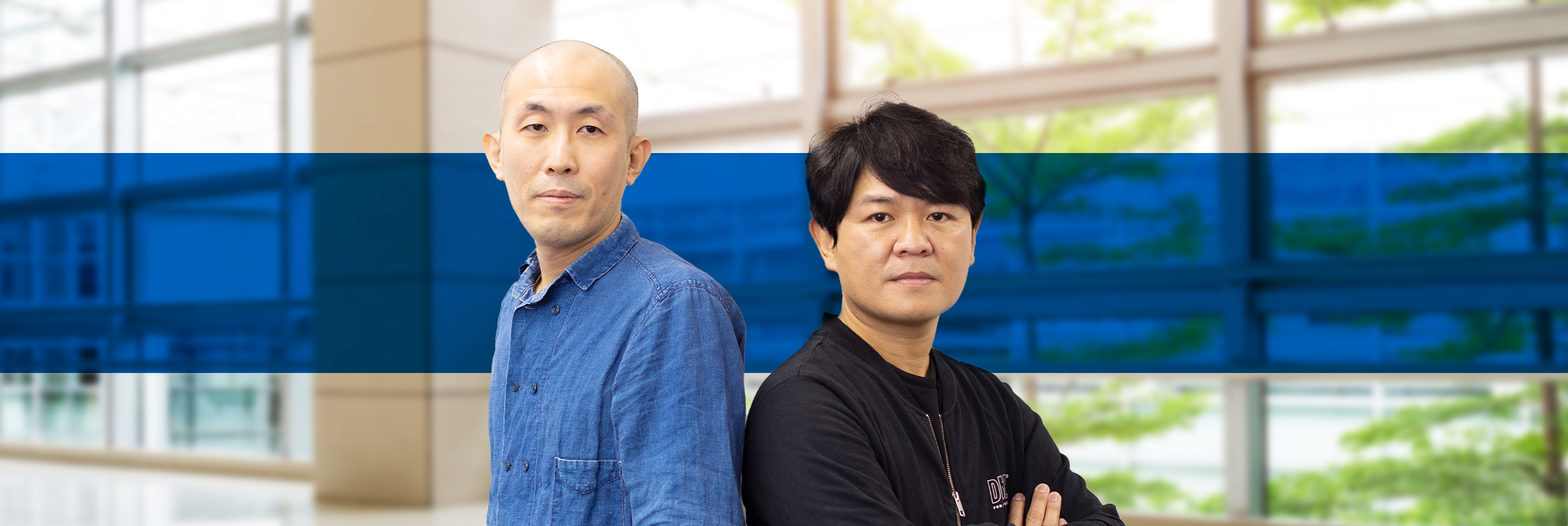
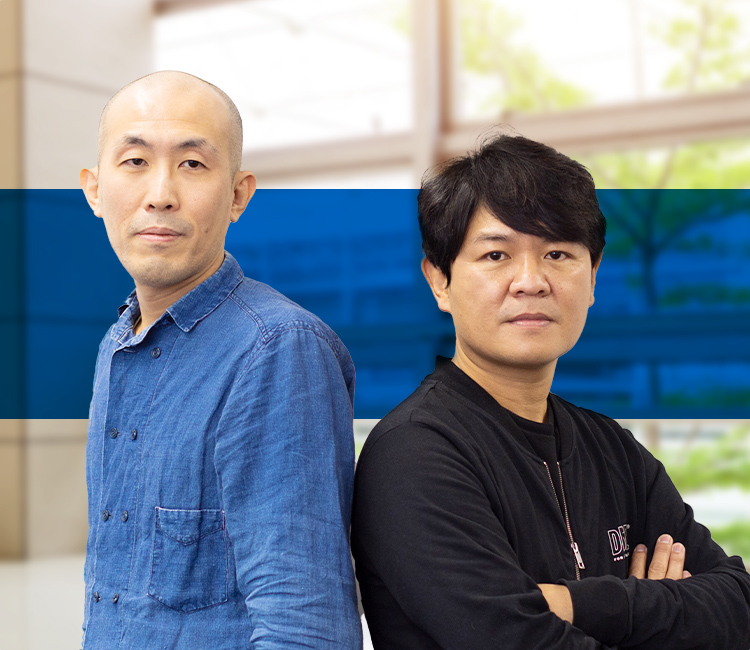
一瀬 泰範Yasunori Ichinose
1998年に入社後、企画担当としてアーケードゲーム開発に携わり、モンスターハンターポータブル以降、モンスターハンターの携帯機シリーズのディレクターを務める。
辻本 良三Ryuzo Tsujimoto
1996年、プランナーとして入社。様々なタイトルに企画担当として携わり、モンスターハンターポータブル2nd以降、シリーズのプロデューサーを務める。
Prologue
2021年1月8日。
体験版の「モンスターハンターライズ DEMO」が配信されたその日、ネット上は夢中でプレイを楽しむユーザーの歓声で溢れていた。
携帯ゲーム機の常識を超えた流麗なグラフィック。これまでのモンスターハンターらしさを強く感じさせながらも、新しいアイディアによって具現化されたテンポの良いゲーム性。その全てが体験版をプレイしたユーザーを狂喜させた。
発売後、750万本を超える売り上げを記録し、2021年度日本ゲーム大賞受賞の栄誉に輝いた「モンスターハンターライズ」。その高みへと至る第一歩が踏み出されたのは、2015年だった──
「次世代携帯ゲーム機で、新しいモンスターハンターを作れないか」そんな相談を、辻本が一瀬に持ち掛けたのは、ようやく『モンスターハンタークロス』の開発が終わった頃。2015年の後半のことである。並行して『モンスターハンター:ワールド』の開発はスタートしていたが、これまで通り携帯機で遊べるモンスターハンターにも絶対に需要はあると辻本は考えていた。そこから『モンスターハンターダブルクロス』の開発に並行して携わりながら、辻本と一瀬を中心にごく少人数のチームで今作のプロジェクトがスタートした。
実は、『モンスターハンターライズ』で導入された新機軸の一つである「翔蟲」と、それを駆使したさまざまなアクション性は、かなり早い段階からコアなアイディアの一つとしてあった。モンスターハンターは、ゲームの核となるアクションの部分がシステムとして完成されている。「逆に言えば、遊びとして固定化されているとも感じていたんです。そこに新たな風を吹き込む手段の一つとして、クエストの中での“手ざわり”から、アクション部分に新しい変化をもたらしたかった」と一瀬は語る。それが、翔蟲を使ったダイナミックなワイヤーアクションだった。
ライズの立ち上げ当初は、開発機材もなかったため、開発途中の『モンスターハンターダブルクロス』を改造しながら、翔蟲を使ったダイナミックなワイヤーアクションをいかにしてゲームに組み込んでいくか、遊び部分の試行錯誤が重ねられていった。

もう一つ、開発の初期段階から明確に方向性が定まっていたのは、「和」の世界観をベースにすることだった。「『モンスターハンターポータブル3rd』でも、和のモチーフを採り入れることにチャレンジしましたが、今回はそういう要素をより強く打ち出したものにしたいと考えていたんです(一瀬)」
しかし、和のモチーフをどううまくモンスターハンターの世界観に落とし込むのかはひとつのキーポイント。「和風だからと言って、忍者ゲームや侍ゲームになってしまってはモンスターハンターじゃない。あくまでもモンスターハンターとして和の世界観をデザインする必要がある。そこは上手くやってくれるだろうと、一瀬やスタッフのことを信頼していました」と辻本は振り返る。
今作で新たに登場したモンスターたちが、日本の妖怪をモチーフにして誕生したのにも、そういった背景がある。設定のベースは日本の妖怪だが、ゲーム内でそういった説明をしているわけではない。だが、ベースとなるモンスターの設定コンセプトが、その世界観に厚みと奥行きをもたらしている。
また、拠点となるカムラの里の建築デザインにも工夫を凝らした。単に日本の建築物そのままではなく、例えば屋根瓦などは、ヨーロッパの瓦のようなウロコ状のフォルムにするなど、さまざまな文化圏の要素をミックスしながら、独自のオリエンタルな世界観を構成している。こうして、これまでにない「和」を強くテーマにした、新しいモンスターハンターの世界観が形づくられていったのである。

とは言え、開発は決して平坦な道のりではなかった。今作は、自社ゲームエンジン「RE エンジン」で開発されたが、「モンスターハンター開発チームとしては、RE エンジンでの開発は今回が初。しかも、Nintendo Switchというハードでの開発も初。何もかもが、初めてのチャレンジでした(辻本)」。
チームのスタッフ全員が手探りの中でのスタートだった。どんな表現が可能なのか、それを実現するためにどんなツールが必要なのか。ゼロからの検証を積み重ねていった。「こだわったのは、やはりグラフィックのクオリティです」と一瀬は語る。「ゲームとしてのプレイアビリティと、クエスト内での絵作りの密度、その両方を限界まで突き詰める戦いでした(一瀬)」
開発も中盤を過ぎた2019年。『モンスターハンターライズ』の開発は、大きく方向転換することになる。『モンスターハンターダブルクロス』以前はエリア制のマップが採用されており、クエスト中にプレイヤーがフィールド上でエリア移動を行うとその都度ロードが入る仕様だった。ハードのパフォーマンスから絵の密度をあげるために今作もそれは踏襲される予定で開発が進められていた。しかし、『モンスターハンター:ワールド』がそういう進化を遂げたように、昨今のゲームトレンドやユーザーニーズを考慮し、開発途中でシームレスステージを採用することに大きく舵を切り直すこととなった。
すでにスタートからかなり時間が経っており、開発上でもかなりの部分が作り込まれている段階である。修正が必要な箇所もあれば、一から作り直す必要がある部分も山ほどあった。それでも、チームのスタッフのモチベーションは高かった。「より良いモノ、より面白いモノを作るという共通のゴールを目指す以上、ゲーム開発というのはスクラップ&ビルドの繰り返しです。その思いをスタッフ全員が共有できていたからこそ、あの段階での方向転換で逆に全員のモチベーションが上がりましたね」と一瀬は当時を振り返る。
『モンスターハンターライズ』には、そんな開発スタッフ一人ひとりの今作に込めた思いやアイディアが、たくさん詰まっている。鉄蟲糸を使ってモンスターに乗って操る「操竜」も、その一つだ。モンスター担当のスタッフから出てきた「モンスターにしがみついて攻撃を与えるのではなく、モンスターに乗って操縦できないか」というアイディアをカタチにしたものである。狩猟の手段としてモンスターを利用するというこの発想にも今作の翔蟲がマッチし、上手くゲームに採り入れることができた。「操竜という仕掛けが増えたことで、クエスト内での遊びのサイクルに変化が生まれたと思います(一瀬)」
さらに、前作までは拠点の中の集会エリアでしか他のプレイヤーと合流できなかったが、今作では拠点となるカムラの里の中ならどこでも、他のプレイヤーと一緒に遊べるようになった。開発当初には通信が切り分けられておらず、その状態でのチェックプレイを行っていた時に楽しかったから、仕様を変更しそのまま実装にいたったものだ。「クエスト以外でも他のプレイヤーと繋がっていることで、よりゲームの世界への没入感が深まります。修練場で他のプレイヤーにコンボの出し方を教えるなど、楽しみ方の幅も広がると思います」と一瀬は語る。
また今作では、研修後にチームにアサインされたばかりの新入社員も大活躍した。なんと、マガイマガドをはじめ、今作で新登場したモンスターはすべて新人や若手のデザイナーの手によるものだそう。「良いアイディアは採用する。それがたまたま新人だったということです。このチームに限らず、カプコンという会社がそういう社風なんです(辻本)」

2020年初頭からのコロナ禍の影響は、やはり大きかったと二人は振り返る。「実質的に2か月ほど完全に開発がストップしてしまった期間がありました。在宅での検証作業などできることを進めてはいたものの、なかなか思うように開発が捗らない時期がありましたね(一瀬)」
発売日が迫る中、最終的な仕上げ段階にはかなりの人員を動員して作業を進めたと言う。「今回のコロナ禍のような不測の事態にも、全社挙げてタイトルをバックアップする体制作りができました。それがカプコンの強みの一つですね(辻本)」
発売前のプロモーションも、今作に関してはずいぶん状況が違った。過去作であれば、体験版リリース前に体験会イベントでの感想や反応をフィードバックできた。しかし、コロナ禍の中ではそういったリアルイベントの開催は難しい。「今作はこれまでにないカタチでの体験版リリースでした。それだけに、ユーザーからどんな反響があるか楽しみでした」と辻本は語る。「シームレスステージをガルクや翔蟲で移動する、今作の新しい部分も好反応だったので嬉しかったです(一瀬)」
初代発売から17年ほどが経ち、現在も2022年夏予定の『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の発売に向けて急ピッチで開発が進んでいる。ゴールは「最高のゲームをユーザーに届けること」と辻本は言う。「ゲームは進化し続けるもの。最高のゲームというゴールも常に遠ざかっていきます。だからこそ、それをめざして走り続けなくては(辻本)」
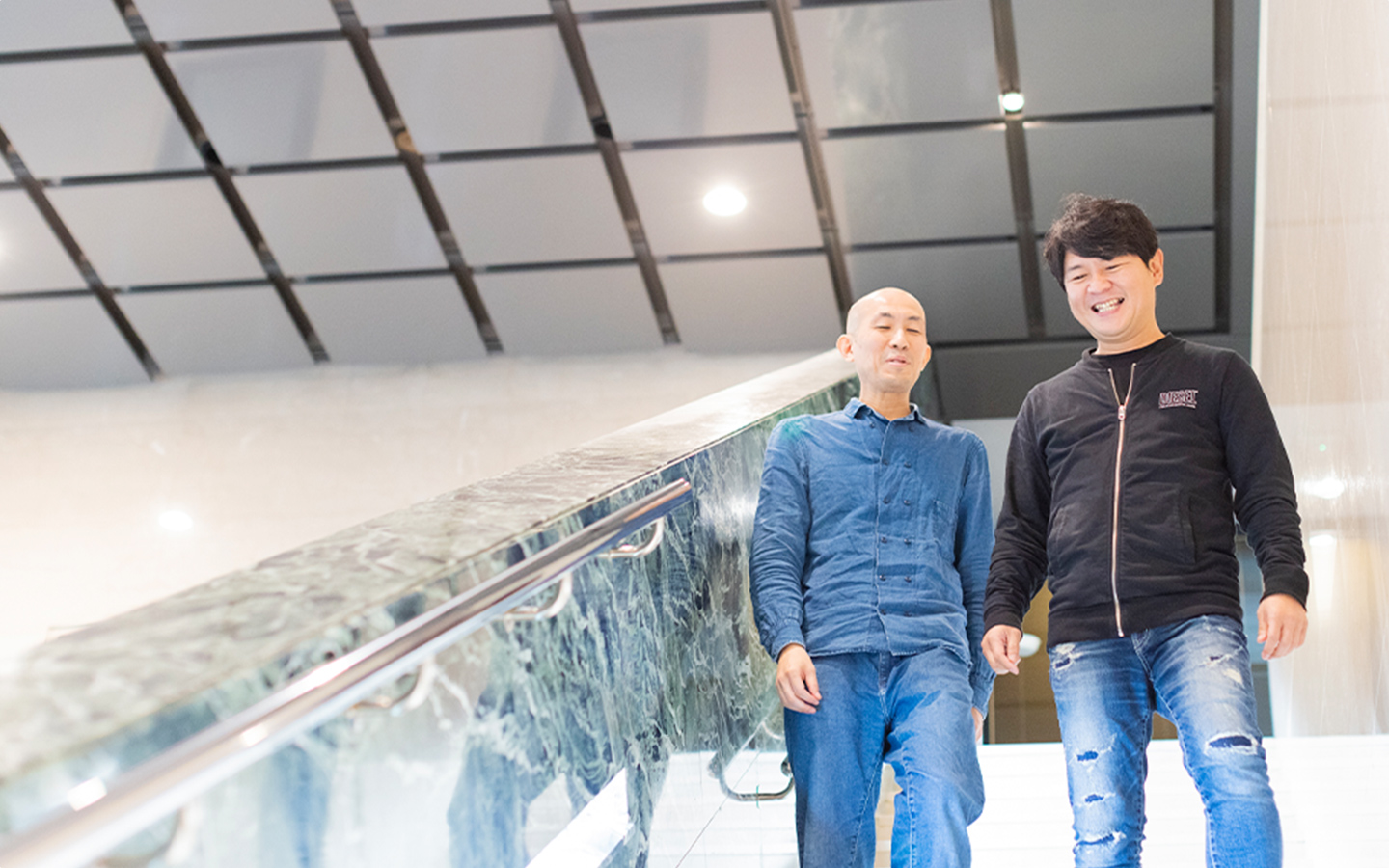
Copyright © CAPCOM CO., LTD. All Rights Reserved.